本公演のテーマ
本公演では、「楽器の持つ可能性を最大限に引き出す」 というテーマを掲げています。ライブエレクトロニクスを単なる補助的な手段ではなく、創作の本質的な構成要素として位置づけることを目指します。
各作品では、従来の枠組みにとらわれない発想によって、楽器の機能や役割を根本から見直す試みが展開されます。これにより、現代の音楽表現における 「楽器」という概念そのものを問い直し、新たな創作と鑑賞の回路を開くことを本公演の狙いとしています。
日時
- 2025年10月4日(土)
- 開場 18:30
- 開演 19:00
場所
FORESTLIMIT
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目8-15
電車
京王新線「幡ヶ谷駅」北口から徒歩1分。北口をでて甲州街道沿を新宿方面に歩き、第一の曲がり角(大通り沿いに赤い郵便ポストがある)を左折。70mほど進んだ右手のビルの地下一階にある。
プログラム
下野優太: 律電体
- Fl. 1 菊地奏絵
- Fl. 2 村上小夏
- Elec. 下野優太
川越康: 拡張楽器 II -for Clarinet-
- Cl. 小林颯樹
- Elec. 川越康
拡張楽器シリーズ2作目。事前収録や内蔵音源を使うことなく、その時に発生した音のみをリアルタイムに加工し作り上げるソロ楽器とエレクトロニクスによる作品。
今回、奏者はクリック音を聞きながら正確に演奏することが求められる。最初に高音の提示された後、鳴る低音の1音が加工されそれが常時鳴り響くことで曲のテンポが決定される。
昭和のような平成のような、海外音楽受容期とシンセサイザーをはじめとする電子音楽黎明期のようなリズムが各所に見受けられ少しのノスタルジアも感じられる作品。
クラリネットの音色と音域の幅を感じ取ってもらいたい。
中村陽太: Chatter/Clatter
- Sax. 吉田谷隆介
- Elec. 中村陽太
Chatter: おしゃべり、機械のカタカタ音、鳥などの鳴き声、通信のノイズなど。
Clatter: カタカタ、ガタガタという音、物音を立てて動くこと、やかましい雰囲気など。
どちらもノイズに関連する語だが、後者のほうがスケールが大きいという大まかな違いがある。
今作ではこの違いに着目し、サンプリング、電子的・物理的ノイズによって生成される音響から楽曲を構成した。
田中孝和: 階の譜
- 薩摩琵琶 中山誠也
- Elec. 田中孝和
「階(きざはし)の譜」を作曲するにあたっての関心は、音楽の中で主題・動機・中心的な素材が時間経過のうちにどのような物語を描くのか、という物語性であった。文芸や音楽、劇、映像作品などで一般的に使われる「クライマックス(climax)」という言葉の語源はギリシャ語の「梯子」であり、修辞学的には文・句・言葉を積み重ねていくことで「ヤマ場」を形成する機能のことである。
本作品もこの古典的な漸層法(クライマックス)に則り、冒頭で提示される動機が小さいレベルからより大きなレベルへと発展・拡大し、「ヤマ場」を形成する。その後終局に向けて、積み上げてきたものが解体され、緊張が緩和していく「アンチ・クライマックス」が用意されている。
渡邉杏花里: Allodynia
- B. Cl. 吉村錬
- Va. 工藤洸大
- Elec. 渡邉杏花里
Allodynia(アロディニア、異痛症)とは、通常痛くない程度の刺激で痛みを感じる症状のことです。偏頭痛の症状の一つでもあり、わずかな触覚や、光・音にも過敏になり、大きく不快なものとなります。
この曲は、自身の偏頭痛の体験からアロディニアの症状を模倣して作曲しました。本来そこまで大きくないはずの音が、コンピューターの処理によって大きく歪められ、その残響がじわじわと続いていきます。
たこミ: 声/呼吸/身体の亡霊
- Sax. 菊池麻利絵
- Perf. 羽鳥直人
- Elec., Perf. たこミ
アウトサイダー/ハイカルチャーといった区分が曖昧になった現代。文脈もルーツも全く異なる3人のアーティストが、複数人の演奏・表現における聴く/聞かれる・見る/見られる・といった相互関係を、音・言葉・身体から捉え直し、知覚とシステムの誤作動を引き起こすパフォーマンス。
全体は3つの異なる性格を持つパートに分かれていて、テキストによりそれぞれの3人の関係性と、大まかな進行が定められている中で、即興的な音や身体のコミュニュケーションを通して空間を考察する。
*演奏会の内容は予告なく変更される可能性がございます。
演奏者プロフィール
菊地奏絵
主に現代音楽、初演、即興演奏、作曲、ジャズ、詩作、映像制作、被写体など幅広く活動し、コンサートや公演のプロデュース、音楽監督も手がける。東京藝大コレクション2023では即興演奏と電子音楽によるパフォーマンスでグランプリと聴衆賞を受賞。パルナッソスwo定期演奏会にゲストソリストとして出演、加藤訓子inc.プロジェクト・スティーブライヒ「ドラミング」ツアーにも参加し、加藤訓子プロデュース公演での現代音楽を中心としたリサイタルも好評。他に音楽、舞踏、美術を融合した「沈黙の惑星」などの自主公演、原田里央の個展や武蔵野美術大学卒展、藝大アートフェス2024での創作活動を展開。11月21日に東京コンサーツラボで若手作曲家委嘱作品も含む自主ソロリサイタル開催予定。フルートを木ノ脇道元、ジャズフルートを片山士駿に師事、東京藝大音楽学部器楽科4年在学中。
村上小夏
8歳よりフルートを始める。第72回全日本学生音楽コンクール全国大会中学生の部第1位。第74回同全国大会高校の部第1位。第40回かながわ音楽コンクール一般の部第2位。これまでにフルートを立花雅和、森圭吾、高木綾子、大平記子、小池郁江、上野由恵の各氏に師事。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、現在東京藝術大学4年次在学中。
小林颯樹
埼玉県草加市出身。3歳よりピアノを、12歳よりクラリネットを始める。埼玉栄高等学校卒業。東京藝術大学に入学し、3年次在学中。現在は大学を始めとする演奏活動や後進の指導を行っている。これまでにクラリネットを𠮷田かなえ、藤井一男、三界秀実、サトーミチヨ、伊藤圭各氏に、室内楽を福士マリ子、吉井瑞穂、萩原麻未各氏に師事。京都フランス音楽アカデミーにてフローラン・エオー氏のマスタークラス受講、選抜コンサートに出演。第40回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校の部1位。第3回Kクラリネットコンクール大学・一般の部3位。第7回K木管楽器コンクール大学・一般の部1位。第11回日本クラリネットコンクール入選。2025セイジ・オザワ松本フェスティバル「子供のための音楽会」に参加。
吉田谷隆介
2002年生まれ。サクソフォーンを12歳で始める。これまでに、サクソフォーンを須川展也、彦坂眞一郎、本堂誠、有村純親の各氏に、室内楽を彦坂眞一郎、松井宏幸の各氏に師事。ジャズサクソフォーンを後藤天太に師事。現在、東京藝術大学4年次在学中。
中山誠也
東京都出身。東京藝術大学、楽理科4年次在籍中。楽理科入学を機に琵琶を始める。伝統的な「語り物」の習得に励むと同時に、器楽曲や他楽器とのアンサンブルにも積極的に挑戦している。また、大学3年次に奏楽堂にてノヴェンバーステップスのソリストを務める。琵琶を塩高和之氏に師事。
吉村錬
福岡県北九州市出身。中学校の吹奏楽部入部をきっかけにクラリネットを始める。福岡県立門司学園を卒業後、東京藝術大学別科を修了。これまでにクラリネットを森卓也、高子由佳、伊藤圭、三界秀実、野田祐介の各氏に、室内楽を吉井瑞穂、西川智也、松原勝也、三又瑛子の各氏に師事。第51回東京藝術大学室内楽定期演奏会オーディション合格。現在東京藝術大学器楽科3年次在学中。
工藤洸大
2005年生まれ。4歳よりヴァイオリンをはじめ、15歳でヴィオラに転向。ヴァイオリンを美尾洋乃、石亀協子、近藤薫の各氏に、ヴィオラを市坪俊彦、大野かおる、鈴木学の各氏に師事。第18回日本管弦打楽器ソロ・コンテストにて金賞・埼玉県知事賞を、第25回日本演奏家コンクールにて特別賞を受賞。小澤国際室内楽アカデミー奥志賀2024年受講生。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、現在、東京藝術大学音楽学部在学中。
菊池麻利絵
東京音楽大学助教。博士(音楽)。神奈川県立弥栄東高等学校音楽コース(現・相模原弥栄高校芸術科)、東京音楽大学卒業。フランス・セルジーポントワーズ地方音楽院サクソフォン科を審査員満場一致の金賞、及び賞賛付きの首席で卒業。また同音楽院室内楽科を審査員満場一致の金賞、ソルフェージュ、アナリーゼ、和声学で最高評価のトレビアンを獲得。帰国後、東京音楽大学大学院音楽研究科博士後期課程に管楽器専攻として初めて合格、給費特待奨学生として学び、2022年3月、野平一郎作曲《息の道》の演奏、論文によって審査員満場一致で博士号(音楽)を取得し首席で修了。『Amazing Saxophone』(音楽之友社)、『Saxophonist』(日本サクソフォーン協会)に論文が掲載される。第7回ナント国際サクソフォンコンクール(フランス)第1位受賞など、国内外のコンクールにおいて入賞。これまでにサクソフォンを村松功介、石渡悠史、小串俊寿、波多江史朗、ジャン=イヴ・フルモーの各氏に師事。株式会社ソニーミュージックエンタテインメント「STAND UP!CLASSIC」メンバーとして、テレビ番組出演等で活動。現在「東京SDGs吹奏楽団」メンバー。P.モーリア(ソプラニーノサクソフォン)公式アーティスト。
羽鳥直人
Instagramで活躍中のでたらめダンスおじさん。毎日様々な踊り方を試し、ダンスの可能性を探求している。
- 主催: 電気羊の部屋
- 助成: アーツカウンシル東京 [スタートアップ助成]


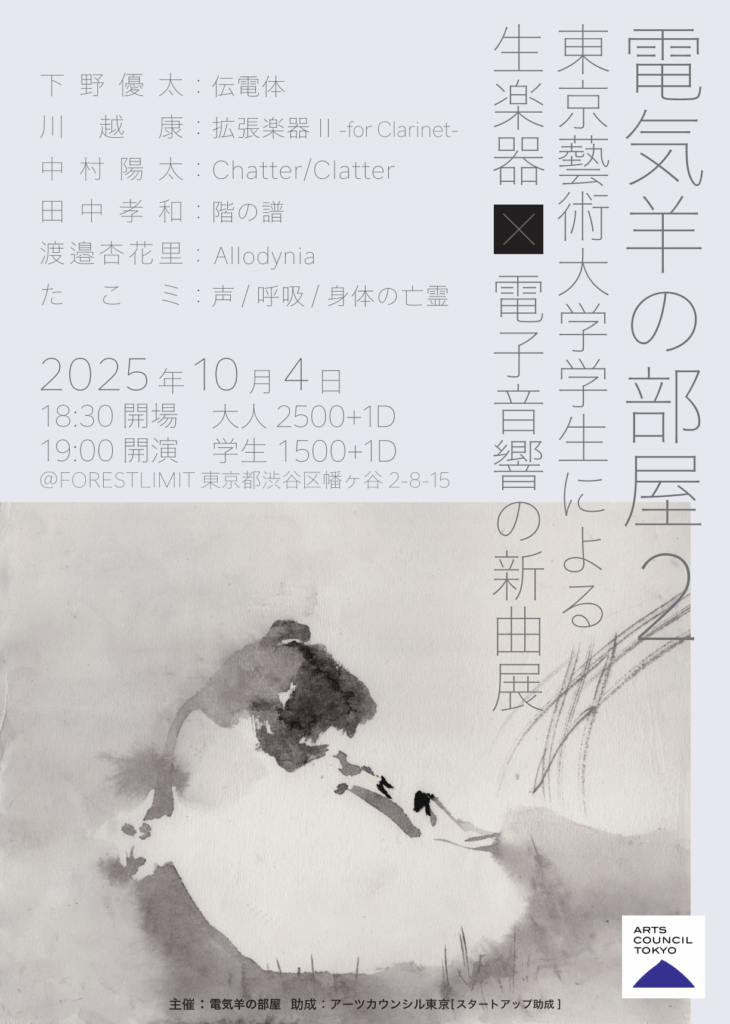
最近の私の関心は、音高一つ一つを「音響素子」として捉えることである。そしてそれらが1つの楽曲として集合体を成すときに、どのような性質を持ちどのように振る舞うべきなのだろうか。
今回はライブエレクトロニクスの演奏会ということもあり、点電荷を音響素子にみたてそれらがどう振る舞うかをシミュレーションしてみた。それらは互いに引力や斥力を持ったり、場合によっては一様な電場により一斉に同じ方向に電荷が動いたりする。Fl.が電荷を放出し、エレクトロニクスがその相互作用を音として表現することにより逆説的にFl.自身からもその相互作用の音が立ち上がるのである。